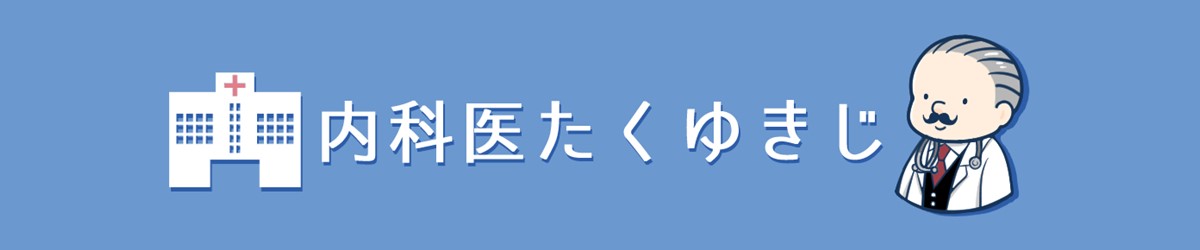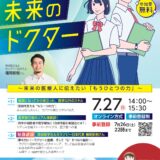こんにちは、たくゆきじです。
今回の記事は「心臓病学会の企画の裏側を聞く」というテーマの記事となります。
なぜこういう記事を書いているかといいますと、実は私は2025年の心臓病学会の広報委員となっておりまして
という使命を担っているわけです(ドヤ顔)
 第73回日本心臓病学会学術集会の情報まとめ
第73回日本心臓病学会学術集会の情報まとめ ということで今回は心臓病学会ならではの企画である
Case Presentation Award
エキスパートに聞く
Retrospective Research Award
というセッションを企画されているJ-NECSTの外海洋平先生、藤野明子先生にお話を伺うことになりました。
外海 洋平 (そとみ ようへい)
大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学
多施設共同臨床研究グループ 主任研究者。
専門はカテーテルインターベンションでありながら、気づけば多領域の多施設共同臨床研究に関わる日々。
大阪を拠点に、日本全国そして世界の協力施設と連携しながら、エビデンス創出に取り組んでいる。
モットーは「一人では何もできない。餅は餅屋。だから、チームで挑む。」
藤野 明子 (ふじの あきこ)
京都医療センター 循環器内科
AMI治療に憧れて循環器内科を志しましたが、近年やや停滞感のある虚血領域であらためて自分の進むべき方向を模索中です。
これまでカテーテルを用いた冠動脈の画像診断に携わってきましたが、最近は二児を育てながら仕事をする中で「効率性」が自分のなかで切実なテーマに。
より低侵襲で無駄の少ない、患者さんにも医療者にもやさしい画像診断に興味を持っています。
J-NECSTができたきっかけ







それでどう盛り上げるか、という議論の中で若手の意見を取り入れた企画を開催する流れになりました。
それで若手向けのセッションを企画するべく集められたのがJ-NECSTです。当時は7、8人でした。



J-NECST(Japanese NEtowrk for Cardiology Specialists of Tomorrow)とは…
日本心臓病学会を盛り上げるために、若手向けのセッションを企画しているグループ。
最初の企画は2つ


前提としてJ-NECSTの目的は、日本心臓病学会を若手目線でもっともっと盛り上げたいな、というものです。
そのためまずは若い先生に学会へ足を運んでもらわないことには始まらない、という視点から企画を考えました。

その目線で企画を考えたとき、やはりAwardは参加するモチベーションにつながるきっかけになるのではないか、と思いました。
もちろん学会のAwardとしてはYIA(Young Investigator Award)がありますが、症例報告に特化したAwardは当時はなかったと思います。


それに研究のYIAは応募対象が40歳までなので、かなり経験を積んだ先生が大きな研究費を獲得し、多施設共同前向き研究などで応募してこられます。
若手の先生がすぐにそうした研究を行うのは、資金面でも経験面でも難しい。
そのため、参加のハードルをもっとぐっと下げたAwardがあればいいのでは、という話になりました。


そうなんです。そこで「Case Presentation Award」を企画し、応募資格を卒後10年目までとしました。
経験豊富な先生方に応募してもらうというよりは、若手の先生方がチャレンジできるチャンスを作りたかったんですね。
これがCase Presentation Awardが始まった経緯です。

応募はなんと120演題













あと過去2年は本戦だけだったのですが、今年は初めて予選を導入するんですよ。
予選を加えることでエンターテイメント性も少し加わるかと思いますので、楽しんでいただけたら嬉しいです。




いえ、さすがにそれはないです(笑)
ただ予選は本戦よりやや時間が短く、端的にインパクトを残すようなプレゼンが求められます。
本戦はもう少し時間が長く、ディスカッションなども含めた総合的な評価になる予定です。

「エキスパートに聞く」のセッションについて


これは私たちJ-NECSTのメンバーで「この先生にこんなお話をぜひお伺いしてみたいよね」という話し合いをしまして、けっこう毎年たくさん案が出るのですが、その中から最終的にはメンバー内で多数決を行って上位の演者の先生にオファーさせていただいています。
去年は心臓血管研究所の山下武志先生など4名の先生にご登壇いただきました。


そうなんです!私も研修医のころから山下先生のプレゼンテーションのファンでして、先生がどんなことを考えてプレゼンテーションを準備していらっしゃるのか、ぜひお話をお伺いしたくて、オファーさせていただきました。
まるで落語を聞いているかのような間の取り方や、スライドに込められた工夫などについて惜しげもなくお話くださって、本当にあの場でしか聞くことのできない貴重なご講演でした。
普通の学会ではなかなか聞けないお話で、つい足を運びたくなりますね。
ちなみに今年はどのような講演になる予定でしょうか?


今年は「学術ジャーナル運営の裏側」「医師の製薬会社勤務」「循環器内科における働き方改革」というテーマで、東海大学の後藤信哉先生、バイエル薬品の新田大介先生、滋賀医科大学の中川義久先生にそれぞれご登壇いただきます。


Circulationのような超一流ジャーナルのエディターとしての貴重なご経験について伺えるということで、とても楽しみにしています。
新田先生の製薬会社勤務のお話も、医師の働き方が多様化している今日、大変興味深いトピックで、こちらも今から楽しみです。


おかげさまでこのセッションは非常に好評をいただいています。
実は来年のJCSでもJ-NECSTの企画枠をいただけたのですが、そこでもこの「エキスパートに聞く」のアンコールバージョンのようなセッションの企画を進めているところです。
大変貴重なお話をお伺いできるセッションなので、ぜひJCSにご参加の先生方にも聞いていただけたらと思っております。


「働き方改革」のパートは、まず滋賀医科大学の中川先生から基調講演を賜ったあと、大学病院⇔市中病院、都市部⇔地方、ベテラン⇔若手、男性⇔女性のように、様々なお立場で現場を切り盛りされていらっしゃる先生方をお招きして討論を行う予定です。


学会などでの働き方改革のセッションでは、病院や診療科のマネージメントをされていらっしゃる、比較的上のお立場の先生方のお話が多いように思いますが、私たちのセッションではJ-NECSTらしく、若手を含めた現場からの意見も十分に反映させた形で、現実的なディスカッションができればと思っています。
まとめ
今回はJ-NECSTの活動にかける、先生方の熱い想いが伝わってくるインタビューでした。

次回の記事ではインタビューではJ-NECSTのもう一つの企画である「Retrospective Research award」についてお届けします。
若手研究者にとって大きなチャンスにもなるこのAwardは、どのような想いで企画されたのでしょうか。
どうぞご期待ください。