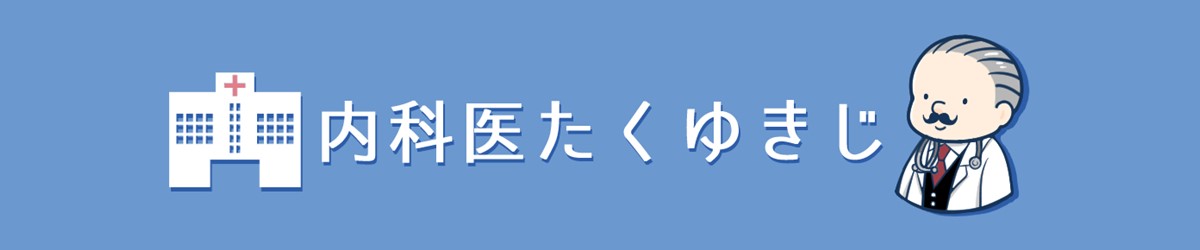こんにちは、たくゆきじです。
今回の記事は「心臓病学会の企画の裏側を聞く」というテーマの記事の後半となります。
 第73回日本心臓病学会学術集会の情報まとめ
第73回日本心臓病学会学術集会の情報まとめ 前回の記事では心臓病学会で「J-NECST」のメンバーが集まった経緯と、その企画である
Case Presentation Award
エキスパートに聞く
についてお話を伺いました。


後半の今回の記事では「若手にとって大きなチャンスになる」と特に力を入れて語られる「Retrospective Research Award」についてお話を伺います。
外海 洋平 (そとみ ようへい)
大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学
多施設共同臨床研究グループ 主任研究者。
専門はカテーテルインターベンションでありながら、気づけば多領域の多施設共同臨床研究に関わる日々。
大阪を拠点に、日本全国そして世界の協力施設と連携しながら、エビデンス創出に取り組んでいる。
モットーは「一人では何もできない。餅は餅屋。だから、チームで挑む。」
藤野 明子 (ふじの あきこ)
京都医療センター 循環器内科
AMI治療に憧れて循環器内科を志しましたが、近年やや停滞感のある虚血領域であらためて自分の進むべき方向を模索中です。
これまでカテーテルを用いた冠動脈の画像診断に携わってきましたが、最近は二児を育てながら仕事をする中で「効率性」が自分のなかで切実なテーマに。
より低侵襲で無駄の少ない、患者さんにも医療者にもやさしい画像診断に興味を持っています。
若手医師の登竜門「Retrospective Research Award」
では「Retrospective Research Award」についてお伺いします。
こちらは「Case Presentation Award」の応募が多かったので、研究部門も作ろうという流れで始まったのでしょうか?






人数が増えできることも増えたので、心臓病学会の年次集会でもうひとつ新しいセッションを企画しようという話になりました。
J-NECSTのメンバーはリサーチマインドにあふれる先生が多いので、何か若手医師の研究に関わるようなセッションにしようと。
そこで若手向けの単施設だけでも始められるような、敷居の低い後ろ向き研究を対象としたAwardを立ち上げよう、ということになりました。
ここも卒後10年目までという設定が絶妙ですね。
YIAのように40歳までとなると、いわゆる「ガチ勢」も応募してきそうですが、後ろ向きでかつ卒後10年目までが対象となると、臨床研究を初めて組んだ先生方からの応募も多そうですね。




それもすごい数ですね!まさしく
「熱意はあるけれど、まだ自信が持てない…」
という先生方のファーストステップになっている感じがします。


大きな研究を若いうちにするのは難しいですが、その前に小さなことからコツコツと基礎を学ぶ必要があります。後ろ向き研究はその最初の一歩だと思っています。
規模は小さくとも、日常臨床の疑問をきちんと検証する、そうしたプロセスを学びつつその努力が脚光を浴びる機会になればと思います。
この経験が将来の前向き多施設研究へとつながる登竜門になってくれると嬉しいです。

Awardの隠れた目的と公開オーディション



はい、そうです。こちらのAwardでは必ずしも完成された研究が出てくることを期待している、というわけではありません。
むしろ鋭い視点から生まれた着想を、どうすれば論文という形にできるのか、という前向きで建設的なディスカッションの場にしたいのです。
自分の施設に研究の良いメンターがいない、という悩みはよく聞きますので。


臨床の疑問について相談できる先輩はいても、研究について相談できる先輩がいない、というケースは多いと思います。
そのためこの「Retrospective Research award」が直属の先輩ではなく、施設の垣根を超えた「メンター」と出会うきっかけになってほしいな、とも思っています。
熱意はあるけれどどう形にすればいいか分からない、という悩んでいる若手にとってすごく勇気づけられると思います。
Awardで競うとなると完成された研究でないと出せないのかな、と思ってしまいますが、そうでなくても、建設的な意見をもらえる場としても活用してほしい、ということですよね。




そうなると演題を出してない若手の先生も、聴講することで「自分がやっている研究、こうすればもっと良くなるのか」という「型」を学べるということですね。
いわば公開オーディションのような場として、演題を出していない先生にも見に来てほしいという思いもあるのでしょうか?


ありがとうございます(笑)
若手の先生もそして指導する立場の先生も、共に学びに来てほしい、という感じなのですね。

過去の自分だったらこのアワードに出していた


私もカテーテルアブレーションに携わっていますので、とても興味深いです!
こちらの研究はどこかのAwardに出されたのですか?


実はこちらはAwardには出していないんです。私は基本的に論文を書くことに関心があって、学会発表そのものにはあまり力を入れていなかったので。
ただちょうど良いAwardがなかったというのも一つの理由ですので、当時「Retrospective Research award」のようなAwardがあったら、絶対に出していたなと思いますね。




私は国循で後期レジデントとして働いていたときに、臨床研究の考え方や統計ソフトの使い方などを一通り学ぶことができました。ただ、どの研究も学会発表止まりで論文という形には残すことができないまま、別の病院に移りました。
その病院はカテーテル治療をたくさんしている病院で、膨大な数の慢性完全閉塞病変(CTO)のPCIの実績がありました。ほとんどの症例で、術前のCT画像をもとに治療の戦略を立てるという方針がとられていて、これは今では割とスタンダードかもしれませんが当時はけっこう先進的な取り組みだったと記憶しています。
そこで術前のCT所見と実際の治療成績がどう関連するかについて、論文にさせていただきました。


先程も出たメンターの話にもつながるのですが、こちらの最初の論文は自分一人の力だけでは論文化できませんでした。
色々な先生の力を借りてようやく完成させることができた思い出深い論文です。
まさに今回の「Retrospective Research award」の裏テーマでもある「メンター」との出会いの重要性を感じさせられますね。
今回のセッションでお二人に「メンターになってください!」という若手との出会いがあるかもしれませんね(笑)


そういうグイグイくる若手は、J-NECSTのメンバーはみんなきっと好きだと思いますよ(笑)
うまくこの機会を利用してほしいですね。
まとめ
いかがだったでしょうか?
心臓病学会の注目セッションである
Case Presentation Award
エキスパートに聞く
Retrospective Research Award
についてお話を伺うことができました。
多忙な中貴重なお時間を割いてくださった外海先生、藤野先生に、心より感謝申し上げます。
このインタビューシリーズを通じて、読者の皆様が日本心臓病学会に興味を持ち、ぜひ実際に足を運んでいただけましたら嬉しいです。