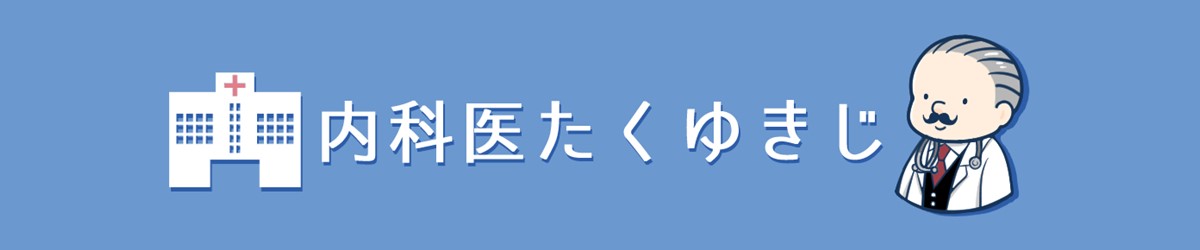こんにちは、たくゆきじ(@takuyukiji)です。
最近思うことがあります。
それは「わからない」ことを「わからない」ということは難しいということです。
この気持ちは医師に限らずだれでも抱くのではないかと思っています。
その心境に関して素直に書いていこうと思います。
研修医の時
研修医の頃は正直何もわかりません。基本的な知識が無ければ経験もないからです。
国家試験の勉強のときに培った知識は土台としてありますが、実務的な内容は本当に何もわかりません。
例えばこの感染症の場合この抗菌薬を使うということは国家試験で勉強しますが、具体的な用量や投与回数はわかりません。
実臨床では具体的な使い方を知らなければ何もできないも同然なので、使い方などを必死になって勉強します。
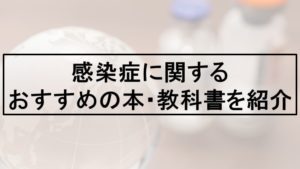 感染症・抗菌薬(抗生剤)でおすすめするわかりやすい本・教科書・参考書
感染症・抗菌薬(抗生剤)でおすすめするわかりやすい本・教科書・参考書 周りの医師も病棟の看護師もそのことをわかっているので、初期研修医に質問する医療従事者は少ないです。
そのため研修医の間は

と言いやすい環境にあると思います。

研修医が空けて
しかし研修医があけるとその状況が一変します。
初期研修医だから知らなくてもしょうがないという状況から専門科を決めた責任ある医師として扱われるようになります。
循環器内科の領域でいうと

と他科の医師から相談をうけたりします。
実際に自分の返事次第でその患者さんの治療方針が変わるので、責任が重くのしかかってきます。



そのため適切な診療方針を選択できるように研修医のときより必死に勉強します。
しかし勉強してもどうしても経験が足りないので教科書やガイドラインではみたことあるけど経験がないので正直自信がないという状況が出てきます。
その場合には同じ科の上級医に相談し、その方針で間違っていないか相談することとなります。
この状況になると自分の専門分野に関してわからないと言えるのは同じ科の上級医くらいになってくるわけです。


専門を決めてから数年立つと
それでもなんとか頑張りながら時間が経つと、それなりに一人でこなせるようになってきます。
今までの経験と照らし合わせて治療方針を一人で決めたりコンサルトにも答えられるようになってきます。
このくらいになると段々と科内の立ち位置も変化します。
具体的には後輩の医師ができて、自分が一番下の状況ではなくなってきます。
こうなると上級医に基本的なことを聞くのはためらわれる状況となります。

と思われているような気がして、だんだん聞けなくなるわけです。
またこのくらい時に意外とストレスなのは研修医や後輩から(自分がわからない内容について)質問を受けることです。
自分が知っていることであればドヤ顔で教えます。

しかし自分が知らない内容について後輩から質問を受けたときは困ってしまいます。
わからないと答えることが恥ずかしいと思う気持ちが芽生え、取り繕ってでもいいからそれっぽいことを答えたくなります。


それでもわからないものはわからない
以前私は後輩からの質問に対して完全に理解していないのにあたかもわかったかのような顔をして取り繕って答えた事がありました。
その後に不安になって調べてみたら違っていたのです。
その後に後輩に連絡して

と伝えました。
このときに痛感したのは取り繕っても何もいいことはないということです。
間違いはいずれバレますし、浅い知識で答えても見透かされると思います。
そのため最近は後輩から自分のわからない内容の質問が飛んできたときには

と答えています。
わからないと言うのは勇気がいります。特に自分の専門分野ならなおさらです。
それでも正直に答えて一緒に調べて知識を共有するのが良いと思っています。


外来でも「わからない」
なお最近は外来でもそのようにしています。
外来で患者さんから質問が飛んできたときは大体答えられるのですが、たまにわからない質問も飛んできます。
懺悔すると曖昧な答えをいってはぐらかしてあとでこっそり調べていたときもありました。
しかし最近は

と答えるようにしています。
患者さんも
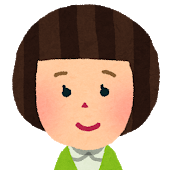
と受け入れて下さる方がほとんどです。
まとめ
わからないことをあたかもわかったかのような顔で答えると、自分が苦しくなる一方です。
努力してわからないことを減らしていくことは大前提ですが、わからないときはわからないと素直に言うと楽になると思います。